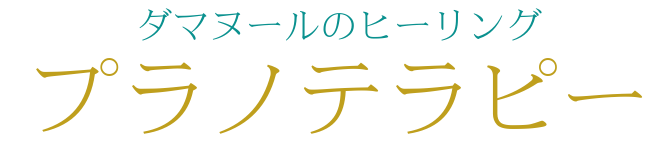自己管理
私たちの呼吸
呼吸を観察する
呼吸は習慣的な行為であり、当たり前のように繰り返される単純なものです。
しかし、呼吸というものをさらに深く観察していくと、それが「膨大な数の微細な動きの連続」であり、「洗練された複雑な動作の中で相乗効果を生み出している」ということがわかります。
このことに意識を向けましょう。
呼吸のそれぞれの一連の動きに焦点を当てるように、意識を集中し、注意を向けてみましょう。
観察用レンズを少しづつ拡大しながら、呼吸の最も微細な部分を探ってみましょう。
吸い込んだ気体のあらゆる分子を一つひとつ注意深く観察し、その経路をたどり、この一見単純で当たり前のように見える行為が、どれほど多くの、そしてどのような身体の部位によって可能になっているのかを発見しましょう。
それが自然静かな行為でありながら、実際にはどれほど複雑で奥深いものであるかを、私たちは発見していくのです。
呼吸についてよく理解するためには、まず呼吸器系に注目することが重要です。
呼吸器系は、鼻、咽頭、気管、気管支、そして肺で構成されています。
鼻は、吸い込んだ空気を肺に届ける際に、湿らせたり温めたりする働きをします。
鼻腔内には小さな毛が生えており、これらは埃やその他の異物が体内に入り込み、体の正常な機能を妨げるのを防ぐ役割を果たしています。
そのため、空気は鼻から吸い込むべきです。
口には有害物質の侵入を防ぐための十分な防御機能がないからです。
口呼吸は、あくまでも二次的な手段として行われます。
息切れしていて、大量の空気が必要な時、鼻中隔の狭い通路を通さずに空気を吸いこむ必要がある時─つまり風邪などで鼻が詰まっている時などです。
どちらも、しばらくすると喉がヒリヒリします。
これは、通常のように、鼻を通って、濾過され、温められた空気ではなく、そのままの空気が喉に触れることに慣れていないためです。
空気は、気管を通って肺に到達します。
軟骨組織で構成された気管は長さ10~12センチメートル、幅約2センチメートルで、左右の気管支に分岐しています。
これらの気管支は肺葉につながっています。
ここで血液中の細胞が酸素を受け取り、二酸化炭素を放出します。
次に酸素は血液によって全身に運ばれ、肺で取り込まれた酸素が体全体に供給されます。
この交換は、生物の生命活動にとって不可欠な前提条件のひとつです。
平均して、肺は1分間に約15回、膨張と収縮を繰り返します。
この動きは、胸郭の底部にある、横隔膜という膜の働きによるものです。
呼吸の速度は、体内の二酸化炭素の量と、密接に関係しています。
運動量、体の緊張状態、空気の清浄度などに応じて、二酸化炭素の濃度が一定のレベルに達すると、脳にある中枢が働き、呼吸の速度を速めたり遅くしたります。
呼吸の状態から自分自身の状態を知る
呼吸の状態を通して、私たちは自分自身の健康についてのたくさんの情報を得ることができます。
短い呼吸は、心理的なアンバランスや、エネルギーの自由な流れを妨げる不安を示しています。
緊張しているとき、不安を抱えている時、息苦しく感じるのは、偶然ではありません。
浅い呼吸、つまり自由に空気を出入りさせることが難しい状態にある人は、外側の環境や他者との交流やコミュニケーションに困難を抱えていることを示しています。
深呼吸は、リラックスして力を取り戻すための、最初の最も本能的な方法です。